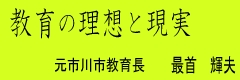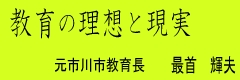トップページ >
「教育の理想と現実」リスト >
2010年
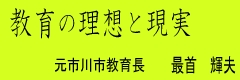
「子供のころの教育環境と経験が人生に重要」
-
「人生は子供時代で決まる」といっても過言ではない。これは自分自身の子供時代と教員の経験から得たもので、今では筆者の信念にもなっている。それだけに、子供の教育においては、教育環境を何よりも重視するのである。
教育環境といえば、乳幼児期は家庭であるが、児童期ともなれば家庭の他に地域や学校へと範囲は急速に広がる。実は、この頃の教育環境が最も重要で、どんな環境でどんな経験をしたかが後々の人生に深く関わる。特に地域社会は、多様な価値観をもった人々の集合体であり教育者の宝庫でもあるから、子供達が豊かな人間形成をするうえで欠くことのできないものである。
昔から「親は無くても子は育つ」といわれてきたが、まさにそうであって、家庭や学校が崩壊しても地域社会が健全でさえあれば子供達は健全に育つものである。換言すれば、地域の崩壊は、子供達の成長の致命傷になりかねないということである。
小欄に前回登場してもらったH君が、子供時代の経験が育てた自分と育ててくれた人々への感謝の念を書き綴ってきたので要旨を紹介する。
大人になった今、「仲間の絆を作る」努力をする自分、思ったことを行動に移せる実行力をもった自分、コミュニケーション力に自信をもてる自分、経験から感謝や思いやりを得た自分を実感している。いずれも、市が実施してくれた「中学生のニュージーランド派遣事業」が「きっかけ」となり、その後立ち上げた「学生会」で培われたものである。行動力もコミュニケーション力も感謝や思いやりも、誰かが教えるものではなく、自分が経験からくみ取って、自分のエネルギーにもう一度回すことができるかどうか、そのことを教えてくれる人や仕組みが地域や社会の中にどれだけあるかだと思う。それが自分の時にはあった。だから、これからも、その「きっかけ」を与えてくれた人々に感謝し、恩に報い続けることになるし、その絆を守り続けていかなければならないと思っている。これまで続けてこられたのは、地域で育てられた私達の地域愛に他ならない。
ところが、最近は成果主義の世の中となり、成果が見えにくい「学生会」や「地域活動」が大事にされなくなってきたと感じている。教育には「待つ余裕」と「あそび」が不可欠と思うのだが。
(2011年1月15日号)TOP PAGE 「教育の理想と現実」リスト
「若者の成長から感じる地域教育の手応え」
-
「僕は市川が大好きなんです。だから最終的には僕を育ててくれた市川に帰って、この街の仕事がしたいんです」。これは、10年前に発足した市民による【市川(地域)教育を創る会】のある例会でのH君の告白で、出席者一同の感動を呼んだ。同時に、彼らの成長を献身的に支えてきた地域の人たちが、地域教育の確かな手応えを感じた瞬間でもあった。
H君は中学生の時、市川市の中学生海外派遣事業でニュージーランドに派遣された。その後、派遣生OBのための「学生会」を立ち上げ、「縦のつながり」づくりに奔走。仲間の絆を強めるだけでなく、市川市のさまざまなボランティア活動にも参加した。なかでも、子供たちの成長を支える地域社会を目指して平成8年にスタートした市のナーチャリング・コミュニティ事業では、子供たちの考えを直接事業に反映するために教育委員会が設置した「子供部会」委員として活躍した。
彼は大学院修了後に民間企業に就職したが、大学院で研究した理想と現実とのギャップに悩み退職。異業種のマスコミ業界へと転身し、いくつもの部署を渡り歩いた。30歳を過ぎ、新しいビジネスモデルのアイデアを求めて社会人大学院のMBAコースに進学。業種も企業規模も異なる学友に囲まれながら切磋琢磨する日々を通じて、強力なエネルギーを受け取ることができたという。そう語る彼の言葉の端々から透けてみえてくるのは、幼いころから地域での大人たちとの出会いを通じ、さまざまな影響を受けながら人間的に成長を重ね大人になった、ということだ。
冒頭の言葉は、彼が執筆した論文が日本新聞協会の懸賞論文で優秀賞に選ばれたことを、同会メンバーに伝えたときのもの。照れながらも感謝の気持ちを精いっぱい伝えようとする姿に、同会メンバーは一様に万感胸に迫るものがあった。
昨年の新年号では新政権への期待を書いたが、早々に失望へと変わった。今年は、国に依存せず、地域(ここでは広くは市、狭くは学区を指す)の自立に希望を託したい。幸い、わが故郷・市川市も行政トップが替わり、教育現場にやっと明るい光が差し始めたと聞く。再び、「人を育てる地域」への復活が期待できる。そこで、市川という地域で育った若者たちに光を当て、その成長を追いながら、「教育とは何か」を考えていきたい。
(2011年1月3日号)TOP PAGE 「教育の理想と現実」リスト
「市外からみる市川教育の『地域重視』」
-
先進的な市川市教育を取り入れたいと要請されて埼玉・深谷市教育に携わることになったS氏に「深谷市にいて、市川市の教育について思うこと」と題して寄稿してもらった。
【深谷市立中学校の「学校相談員」となって8か月余りが過ぎた。深谷市の学校相談員は市川市に当てはめると、各小学校の「ゆとろぎ相談員」が中学校区の児童・生徒とその保護者の相談に応じる―というイメージである。ただ「学校相談員」はあくまで「学校の人」であり、「ゆとろぎ相談員」は学校の中の「地域の人」という位置づけの相違がある。相談室の利用方法も相談室登校生徒の自習や悩みごと相談が中心で、市川の「遊びを通して子供を育てる」は理解されない。対策と予防の違いである。
深谷市はお祭りが盛んで、大人同士には人生を楽しむ気質が感じられる。広大な土地に恵まれ工・農業も盛んで、地方としては豊かな地域といえる。渋澤栄一翁を仰ぎ、代々の市長の「教育に金は惜しまない!」という方針に学校教育も支えられている。地域の活力も教育への関心も強いが、なぜか埼玉県内で不登校生徒が増加傾向という実情もある。市川市教育委員会発信の「学校・家庭・地域」は今日では全国共通語になり、深谷市でも式典などの挨拶(あいさつ)の度に聞かれる。しかし『地域重視』を聞くことはない。
転居後もナーチャリングコミュニティなど、地域で一緒に活動してきた仲間からメールが届く。子供たちの問題が表出した時など「自分たちの力が及ばなかった」「かかわってきた子供達が成長した。彼らと一緒に困っている子供たちに声をかけていきたい」と、いずれも地域の子供たちの問題は地域の大人たちの責任であるという前向きで強い信念が伝わってくる。そして市川の『地域重視』の歴史と成果を感じる。
古今東西、思春期の子供たちの問題は家庭では手に負えないところが多いものである。問題の発生から解決までが、学校生活の時間や期間の中で完結するだろうか。中学校を卒業していく子供たちの背中は心細げなものである。幼いころから親しんだ地域の大人たちの見守りの中で、緩やかに成長できることこそ、子供の幸福といえるのではないだろうか。これが私の知っている市川の風景である。これからも永遠にこの情景が拡がっていくよう、そして絶えぬよう祈りたい。】
(2010年12月18日号)TOP PAGE 「教育の理想と現実」リスト
「地域で育った子供は、地域を大事にする」
-
子供たちを取り巻く教育環境の悪化による人間性の欠落、感性の衰滅など、極めて憂慮すべき状況を何とかしたいと、1975年から「地域教育力の重要性」に着目した施策に取り組み、全国に発信した市川市。その市川で子供時代を過ごした、建築学を学ぶ24歳のT君のこれまでの姿から、当時の市川教育を振り返ってみたい。
T君は小学校6年生のとき、市川市で始まったナーチャリング事業の子供部に参加。その年、小・中学生約20人が主体となりフェスティバルを企画実行し、その一人となったT君は「中学生と同等に自分達小学生も一緒に内容を考えて実際に運営もして、あの時は一気に大人になった気分だった。大人も自分達を大人扱いにしてくれたことが嬉しかった」と述懐している。
T君達は高校生になると、中学時代の仲間30人ほどに声を掛け〝地域で文化祭〟を実行した。準備不足などを批判する声もあったが、「我々はイベント屋ではないはず!今時、高校生が30人も集まって自主的に自分の育った地域の子供達と一緒に行事を開催するなんて、それだけで意味がある」という大人達の声が、その後の彼らの活動を後押しした。以来、T君達は地域の同級生以外にも、高校や大学、専門学校、趣味の仲間達を誘い、文化祭的なものや運動会、キャンプ、果ては自分達で祝う成人式まで実行した。
T君達は今年の初め、市川で地域活動のリーダーとして活躍していた埼玉県に住むS氏の元を、卒論の報告がある―と訪ねた。卒論の課題は〝仮想の街づくり〟、キーワードは『地域』『小学校』『子供』で、「これ以外のテーマは自分にはなじまなかった」という。
もう一人、T君と同行してきた当時の仲間Rさんは現在、大学病院で看護師・助産師、更さらには高校生の性教育講座の講師として活躍している。彼女は「いまは大学病院という恵まれた医療環境で働いているが、ここで身に付けた力で、いずれはもっと地域に根差した働き方をすることが夢!」とはにかみながら話してくれた。
成長途上の若者たちと再会し、いままた市川市を振り返り、「ナーチャリングの理念『子供を育てる地域の創造』は、『地域で育った子供は地域と子供を大事にする』ものなのだと改めて実感した」とS氏は語る。これこそ、市川教育の目指したものである。
(2010年12月4日号)TOP PAGE 「教育の理想と現実」リスト
「市川教育の原点、福井で花開く」
-
市川で芽生え育った『学校・家庭・地域の三者が一体となって子供を育てる教育』が、福井で『学校・家庭・地域が連携した三位一体の教育』として見事に開花している。
福井県と市川市の関係は10数年前、敦賀市の教育長と教育委員が市川市の教育を学びたい―と来市した時から始まる。その後も、市川市教育施策の中心的リーダーや千葉県教育ビジョン策定委員を務めたS氏(現、埼玉・深谷市立中学校・学校相談員)が福井県教育研究会の講師として招聘(しょうへい)されるなど、市川市と福井県との関係は深い。
その福井県が全国学力テストで秋田に次いで3年連続上位、昨年度の全国体力・運動能力テストでも1位の実績を上げた秘密を、『ネコの目で見守る子育て―学力・体力テスト日本一!福井県の教育のヒミツ』(小学館)の著者・大田あやさんの話(日経新聞2月25日朝刊)から探る。
福井県は出生率、三世代同居、夫婦共働き率や貯蓄額が全国でもトップクラス。取材してみえてきたことは、大人たちの教育に対する「思い入れの強さ」で、学ぶことを大切にしているから学校への信頼や教師への尊敬の気持ちも熱い。大都市によくある学校や教師への不信感や不満は殆ほとんど聞かれない。興味深いのは、リビングで勉強する子供たちが多いこと。自主性を大事にしながら家族が見守り、子供たちは見守られていると感じる。これが子育ての基本だと感じた。
もう一つ、三世代同居率の高さも子育てによい影響を与えている。祖父母が「学校は大事、先生は尊敬しなさい」と教えるから、父母も些細(ささい)なことで学校にクレームを付けない。祖父母は『学校』『家庭』『地域』のつなぎ手的な存在。また、祖父母が家を守り孫の世話をしてくれるから、母親は安心して子供を産み育て、働くことができる。これが共働きや出生率の高さにつながっている。
更(さら)に、地域住民はスポーツや読み聞かせなど様々なボランティアで学校や教師を支えている。給食を地域ぐるみで作り、地産野菜や地元・越前陶器を食器に使うなど、地産地消の給食で郷土愛を育てている。
このように、学校と家庭、地域が協力して子育て・教育に力を注いだ結果が、学力・体力の成績に反映されたといえる。そして、郷土愛の中で育った子供たちは、自分も故郷で子供を育てたいと思う。これが福井教育であり、市川教育の原点でもあったのである。
(2010年11月20日号)TOP PAGE 「教育の理想と現実」リスト
「教育の再興は3つの「つながり」から」
-
子供の学力格差を生んでいる主要因が『つながり』にあるという。
昨年、大阪大学の志水宏吉教授とその研究室が1964年と2007年の全国学力テストの結果を比較分析して明らかにした。それによると、64年の時点で子供の成績に大きく関与していたのは経済的・文化的豊かさを示す指標であった。所いわゆる謂、都市部と地方との間の「都とひ鄙格差」(当時、学力格差は都鄙格差に由来するという結論が出ている)で、一般的には都会は高く田舎は低いといわれていた。つまり、教育・娯楽費の割合や大学進学率との相関が高かったのである。
ところが、07年のデータ分析からは経済的指標の影響とは異なる指標が子供達の学力に大きく影響していることが分かった。それは「持ち家比率」「離婚率」「不登校率」という3つとの相関である。分析によれば、持ち家比率が高いということは、数世代にわたってその地域に住んでいることから『地域とのつながり』が豊かであること。次に、離婚率が高いということは、少なくとも子供達にとっては生活の不安定さや家族関係に揺らぎを生ずる。即ち『家庭とのつながり』の問題が出る。3つ目は、各種要因が絡むとしても、不登校率が高いということは、『学校とのつながり』の希薄化を予想できる。この3つを総合して『つながり格差』と表現し、これら『つながり』が豊かな自治体の子供達の学力は相対的に高いとみている。この50年の間に学力格差を生む主因が『都鄙』から『つながり』へと移行したというのが、志水宏吉研究室の結論である。
最近の学力格差論は圧倒的に『経済格差』を主因としているが、学力差を経済格差のせいにしている限り解決は困難である。しかし、「3つのつながり」を豊かにすることは、大人達が本気で努力さえすれば一定の成果は出る。事実、全国学力テスト第1位、2位の秋田県や福井県がそれらの条件を満たし結果を出している。テスト結果が悪いのは家庭の経済状態の差だとか教員の質の差だなどと的外れな議論をしているようでは、その地域の教育の質が上がることはない。家族団欒らん、地域の付き合い、教師への信頼などを取り戻すことで、子供達が安心して学べる環境になる。
現代の日本社会が抱えている『つながり』の衰滅を止めることから、教育の再興が始まるのである。
(2010年11月6日号)TOP PAGE 「教育の理想と現実」リスト
「人間性の欠乏が生む、教員の質の低下」
-
日本の教員の質が低下した背景には、日本人の質の低下という根本的な原因がある。
かつて日本人は勤勉で誠実、親切で思いやりのある国民といわれていた。つまり、人間性が豊かだったのである。それが、経済の高度成長を境に諸外国からエコノミックアニマルと揶やゆ揄され、財力にものをいわせて問題をお金で解決しようとする日本―という汚名を着せられ、次第に国際社会からの信頼を失っていく。この過程で教育も本来の教育である人間(人格)形成・人間性の教育から、受験・入社試験の為ための知識中心主義に転化してきた。人間形成を疎おろそかにされた日本人の多くが今、社会の担い手になっている現実を考えると、日本社会は如い何かにも寒々しいという気持ちになる。
広義の教育は、社会に於おける人間の形成作用全般を意味する。こういう社会で育つ子供達がどういう日本人になるかは想像に難くない。所いわゆる謂、連鎖である。
遡さかのぼること20余年、1980年代後半には既に、家庭や地域の教育力の減退による子供達の発達阻害条件の増大が指摘され、学校も能力主義的選別教育に陥り、人間性の育成に欠けるとされていた。その頃ころから子供達の教育環境が劣悪であり続けているのである。その結果としての日本人の人間性の欠乏である。
もう一つ見逃してはならないのが、現代文明人の『感性の衰滅』である。感性は快・不快の主観的体験で、
「快(報酬)不快(罰)は相互に影響を及ぼし合うものであり、不快を克服してこそ真の快(喜び)を得ることができるものであるが、人間は文明の発達による便利で楽な生活を求め、簡単に『快』を得られるようになることで『不快』に対する不寛容性を増してきた。つまり人々は快を求め不快を避けるようになったのである。その為、欲求を手軽に直ちに満足させようとし、後にならなければ『快』をえられそうもない仕事に励めなくなっている」
(ローレンツ著『文明化した人間の八つの大罪』)。
このことは教員に限ったことではないが、教員がその使命である子供の人間形成を放棄し、学力向上という極めて容易な目標を掲げ、ただそれだけで達成感を味わうというのでは余りにも情けない。極言すれば日本の教育の危機である。関係者だけではなく全ての大人が教育とは何かを、その原点に立ち返って考え直したい。
(2010年10月16日号)TOP PAGE 「教育の理想と現実」リスト
「国主導の教育改革が生む組織適合型教員」
-
組織適合型教員は何い時つ頃ごろから増加し始めたのか、それはなぜなのかを筆者の記憶から辿たどってみる。
1980年代半ば、市教委で人事を担当するようになって傾向を知る。90年代に入ると校長・教頭の人事にも関かかわるようになったが、学校教育の最高責任者である校長ですら自ら教育を構想せず教委等に依存し、また、教職員を育てるのが使命であるはずの校長から、良い人材が貰もらえないため学校運営ができないと言い出す者まで現れるようになったのには驚いた。
一方で、教員の栄達志向の強まりが目立つようになったのもこの頃だ。それまでの教員はどんな時でも子供に真正面から向き合い、社会・時代の変化を敏感に感じつつ子供の将来の幸せを見つめ、同僚と切せっさたくま磋琢磨して行動してきたと思うが、時代の変化とはいえ余あまりにもかけ離れた現実に戸惑うこともしばしばであった。
では、教員の急激な質の低下はなぜ起こったのか。前回、油布佐和子早稲田大教授のレポートでも紹介したように、国による教育制度改革、中でも教員評価・管理制度の導入と学校運営体制の強化、及および教育内容・教科書までを国が規定するというものが、学校・教員の自主性や創造性を奪い、従属的・依存的教員を作り上げたという分析は筆者も同意見であり、これが国の狙いでもあることは本欄にも書いた。
世界各国では70年代から教育改革が進められてきているが、共通してみられる基本的方向は全国民参加であり、教員や教育・心理・哲学など専門家による研究・調査・実験の過程を含み漸進的に進めるというものである。
それに対して日本の場合は、全国民どころか教員でさえ参加する機会がなく、企業代表や政権寄りの学者などで構成した再生会議のようなもので方針を正当化し、国主導で性急に事を運ぶというのが実態である。これでは、教員が自ら教育の在り方を思考し行動する必要を感じることは無く、国や教委の方針や指示通りに働き、責任は上位に委ねるという組織適合型になるのも無理からぬことである。そして、官僚や役人がそうであるように、組織の役職上位を志向するのも自然の流れなのかもしれない。
しかし、子供の人間形成の一端を担う学校が仮にもこのような教員の集合体であるとするならば、真の教育が行われているとは言えないであろう。
(2010年10月2日号)TOP PAGE 「教育の理想と現実」リスト
「組織適合型教師では心許ない」
-
教師への信頼が昔に比べて大きく低下している中で、意外にも遣やり甲がい斐を感じる教師が増加している(油布佐和子早稲田大教授、日経新聞1月25 日付)。昨年の調査では「教師になってよかった」が90%を超え「やり甲斐がある」も95%を超えているという。但(ただ)し、油布教授の分析結果によれば「彼らは『子供の人格のあらゆる側面にかかわる』ことや『生徒に自分の体験談や人生観を話す』といったことは少なく、『学級づくり』といった側面にも大きな関心を払わないが、学校の役割は学力向上にあると強く認識している。現在は学力向上を学校目標に掲げている学校が殆(ほとん)どだと考えられることから『学校目標へのコミットメント』が遣り甲斐につながっていると見ることができる」というものである。
更(さら)に、同僚関係も同様の傾向がみられ「同僚と教育観や教育方針について話し合うといった教師同士の実践的日常交流は減少して『組織成員としての交流』に変化してきた。このことは、まさに教師としての質の低下である。これら教師の変化は今世紀に入って急速に進んだ教職改革、教員評価制度導入と不適切教員への人事管理システムの導入、更に、職員会議の法的根拠の明確化、主幹教諭の配置など学校運営体制が再編され、教師の日常的活動を規定する領域が大きく変容したことによる」としている。
その上で「このような組織適合型教師の増加を手放しで歓迎することはできない。それは判断や決定を組織の上位に委ね、自ら教育の在り方を構想することができない末端技術者としての教師が増えることを意味しているからである。現場の複雑さや多様さに応答すること、教育の公共的な使命を考え、長期的なビジョンを持って実践することが教職の世界から排除されていく可能性が高い。子供の実態に向き合っている教師同士が互いに状況を共有し議論を重ね、社会・時代の変化に敏感でありつつ『考え、行動する教師』の育成と学校現場での条件整備が求められる」と結んでいる。
全くその通りで、このような教師の定着が進めば、日本の教育が一段と時代と世界から大きく取り残されていく原因となりかねない。世界的にどの国も教育の変革は子供と直接向き合う現場教師が原動力となっていることを考えた時、これでは余りにも心許無い。
(2010年9月18日号)TOP PAGE 「教育の理想と現実」リスト
「子供から離れて行うべきでない教員研修」
-
教員の信頼回復には、現在行われている形式的な研修制度の改革も必要である。例えば、多額の予算をつぎ込んで制度化した初任研修には決定的な欠陥がある。初任教員にとって最も重要なのは子供理解であり、子供達とは常に一緒にいてお互いに心を通わせ絆きずなを強くしていく体験が必要である。少ない時間とはいえ子供から離れることは避けるべきだが、その為ための配慮(最低でも教員増による少人数学級の実現や教材研究の時間確保)がなされていないままの実施である。真の教育の実現を目指すならば、教員自身の人生経験がまず豊かでなければならない。勉強中心で生活体験の乏しい現代の新任教員から子供との新たな体験の機会を奪い、意味の無い研修をすることは徒とじ爾としか言いようがない。
また、新しく制度化された問題教師排除目的の教員免許状更新制度にも大きな問題が潜んでいる。大学に再入学し、理屈を学び直し、単位を取ることが教員の質の向上になるとでも考えているのだろうか。もし本気で質の高い教員を求めるならば、教員養成課程と教員採用の在り方を根本から考え直すことではないか。
一方、民間では、教員の質を高めるための研修がNPOなどによって組織され、実践研修を通じて現職教師の力量を付けることに成功している例が数多くある。その一つが市川市に事務局を置く《気づき》教育実践研究会。代表の安達征勝氏は人間教育重視の人である。会員は首都圏の私学30校の教員で構成され、月一回の実践研修会が催される。現在はネパールとの教育交流にも発展し、両国の教育で欠乏していることは何か、魅力ある学校になるためにはどうしたらよいか―が活動の出発点。その先には「先生が生き生きしていなければ、生徒は生き生きできない」というこの研修が目指すものが見えてくる。テーマは《気づき》(『つながり』を通して自分という存在を考える)。命、空気・水・食物、時、場、経験などから自分とは何かを考える。教師だけではない。子供たちにも考えさせ体験させるという実践活動を交換し合い、共に教師としての力量を高め子供にそれを還元するという良い循環が起きているという。
このように、真に教員の資質向上を考えるならば、現職研修は子供から離れて行うものであってはならないと思うのだが。
(2010年9月4日号)TOP PAGE 「教育の理想と現実」リスト
「教員の採用・養成制度に問題」
-
日本で教員が尊敬されないもう一つの理由は、教員の養成と採用制度に問題があるとみている。
教員養成は、フィンランドをはじめ欧米のような特別な制度がない。どこの大学でも単位さえ取れば誰でも教員免許状を取得できるので、教員志望で無くても取り敢えず教職課程で単位をとっておこうかということが許される。つまり、教職に対する意欲や情熱の如何(いかん)にかかわらず教職の道に入ることが可能なシステムなのだ。例えば希望する職業に就けないから教職でも選ぼうかとなる。これが所謂(いわゆる)〝デモシカ先生〟誕生になる。加えて、免許状を持っていない人でも教員や校長になれる制度もある。
フィンランドは教師の100%が初めから教師志望で、ここに大きな違いがある。また、教師の殆(ほと)んどが高校を卒業して一度社会に出た後、大学の教職課程で学び教員免許状を取得する。しかも教師志望者(保育士を含む)全員が修士号を得て教員採用試験に臨む。フィンランドでは教師になることは人々の憧れであり、国の未来を支え社会を築いていく若者を育てるという使命を自覚しているからこそ、社会経験を通じて自らを磨く必要があるのだという。
この考え方は教師になっても変わらない。常に新しいことに挑戦し、子供と共に伸びていく教師を目指しているというが、背景にはフィンランド人の一つの価値観がある。それは「社会のデザインと教育プランが見事なほど一致していることだ。どういう子供を育てたいか、どんな社会をつくりたいか、そのため教育はどう在(あ)るべきか、ということが国レベルから現場レベルまで一貫している」(増田ユリヤ著「教師の育て方」岩波書店から)というのだ。政治も国民から信頼されている。二つ目は教員採用制度にある。フィンランドでは教員採用権は校長にある。従って、どんな教員を採用するかがその学校の質を決めることになるので、校長の責任は重い。
一方、日本の教員は都道府県教育委員会が採用を行い、市町村教育委員会を経て各学校に配置される。つまり、地域性や学校のニーズを無視した一括採用であり、学校としては、どんな教員かは来てみないと分からない。更(さら)に、定期異動の制度がある。これらの仕組みを変えない限り、教員の信頼性が高まり尊敬されることは無いであろう。
(2010年8月21日号)TOP PAGE 「教育の理想と現実」リスト
「責任だけ背負わされる教師」
-
現在の日本では、教員の社会的地位は決して高いとはいえない。何なぜ故なのか。よく言われるのが、学歴志向の強い日本人から見れば、昔ほど教員が飛びぬけた学歴を持つには至らなくなったからだという。また、日本人の職業観においても、教職が比較的低位に見られるという傾向にあるからだともいう。
本来教員は、人を教え育てるという崇高な立場にあるべきものであるが、日本では教職を単なる職業の一つとして選ぶという風潮が無いわけではない。『デモシカ先生』という言葉まで生んだ日本社会からすれば、教員が見下されて当然なのかもしれない。しかし、このことが教員の評価のみに止まらず、日本の教育全体の信頼性を欠くことにもなれば放置できない問題である。
筆者は教員の地位低下を単に学歴や職業観に起因するとはみていない。背景の一つには政治や国民の教員に対する評価の低さがあるとみる。原因となったのは戦後の教育制度改市川市民代表として初めて被爆地・長崎に派遣いのうえいさむ市川市真間革。1956年、民主的な旧教育委員会法に代わって『地方教育行政の組織及び運営に関する法律』から始まり次々に教育関連法案を成立させ、教育の国家主義化や教職員の管理強化を進めてきた。教育内容、教育計画から教科書まで教育のすべてを画一的に行う国(現・文科省)主導、上意下達の管理システムを確立し、文科省・都道府県教委そして区市町村教委・学校(校長)という指示・命令系統によって徹底を図り、従わなければ罰するというものである。このような状況下での教員は教育についての自由も裁量権もなく、管理される中でひたすら国で決められた教育内容を一定の教科書を使い、一定の時間の中で子供たちに如いか何に多くの事を教え込むかを考えざるを得ない。その上、教育環境の違いは無視し、子供の成績が悪いのは一律に教員の力量の無い結果だとして責任を負わされる。それだけではない。次々と社会問題化してくる子供の問題をその悉ことごとくが学校・教員の責任であるという世論作りをしてきた。
国家主導でありながら国も地方教委も責任を取らず、全てを学校現場に押し付けるというのが日本の教育制度。自由も権利も無い教員が責任だけを取らされるのはどう考えても不条理というほかは無い。教育政策の間違いまで教員や学校が責任を背負わされる今の日本社会では尊敬される教師は育たない。
(2010年8月7日号)TOP PAGE 「教育の理想と現実」リスト
「フィンランドの優れた教師の育て方②」
-
フィンランドの教師の力量が優れている理由は、教師の社会的地位の高さとその養成過程にある。
教員を志望する者はまず、大学などに設置された教員養成学科に入らなければならない。全国で20個所あるが、希望者が多く狭き門だ。どの大学に入るにしても最初に共通試験を受ける。内容は教育学や発達心理学など5種類の専門書を読みこなした上で自分の考えを綴(つづ)るというもの。合格者は更さらに大学独自の入試を受ける。そこでもかなりの者が不合格となり最終的には13倍程度の倍率となる。
では、どんな教師に育てようとしているのか。フィンランドでは、子供たちが自分の人生に役立つ情報を選びとり、理解し、実際の生活で使える力を養うことが重要と考えている。その後押しをするのが教師の役割であるとして、その為(ため)の指導力を身につけさせる。また、人はそれぞれ違う個性を持つが、それをどう組み合わせてどう生かしていくかがこれからの時代に求められる能力であるととらえ、そうした力を子供たちにつけることのできる教師でなければならないという。具体的には、一つのテーマに関して様々(さまざま)な科目からアプローチすることで関連付けて学ぶ総合学習の指導力と、子供がそれぞれに自ら効果的な方法を常に考えていけるようにすることを教員養成では最も重視する。教科の枠を取り払い、いろいろな方向から物事を見ていく学び、つまり「総合的な学習の時間の指導力」を高めていかなくてはならないと考えているのである。
これらの力を付けるために教育実習が重要視される。担任になるには12週間・最低312時間、教科担任の場合は19週間・530時間の教育実習をする。延長も可能。現場実習重視の理由は、理論だけ学んでも現場では当てはまらないのが教育であり子供であるとの考えからくるもので、教師を現場の研究者と位置づけている。教員は誰もが修士の資格を持ち、教育以外の専門分野でのプロとしても引く手数多(あまた)だという。教員採用権を持つ校長も採用したい教師は、好奇心旺盛で何かのプロとして能力に長け、人間関係が円滑で自然体な人、人間的にも魅力的で信頼を集める人物がよいという。
このように教員の質を重視するフィンランドでは、例え教員不足であっても、質の低下を招く資格の乱発はしないそうだ。
(2010年7月17日号)TOP PAGE 「教育の理想と現実」リスト
「フィンランドの優れた教師の育て方①」
-
「教師! 教師! 教師!」。これは、フィンランドの教育が優れているのは教師の力量が全すべてだというフィンランド国民の合言葉である。教師達の社会的地位は非常に高く、国民から信頼され、尊敬されているという。
では、そういう教師達がどのように養成されているかを増田ユリア著『教育立国フィンランド流・教師の育て方』(岩波書店)から紹介してみよう。教育についての教師共通の理念は「国を支えていくのは若者で、その若者を育てるのは教師である」というもので、これが教師にとっての最大のモチベーションであり、皆、教師であることに誇りを持っているという。そして何よりも実生活に使える力を養うことが教育の重要な役割と考えている。その為ためには人を思う心(人間性)を育むことを第一に、一人一人の持つ力を大切にし、協力し合って一つの社会を築いていくことのできる人間を育てるのだと。元々、社会というものは違った能力や技術を持ち合わせた人たちの集まりであって、互いに違う個性を認め合い、補い合って社会が築かれていくものである。だから社会を築いていくには違った能力や個性を持ち合わせることが有効であって、一つのこと、例えば学力で競って相手を潰つぶしたりするのは無意味であり、比較の争いは不健康であると考えている。従って、教育で大切なことは『みんな違う』ということ、その違う個々の個性や技能、コミュニケーション能力をどう生かしていくかが大切だという共通認識がある。このような教育観を持つフィンランド人は、国際テストで世界一になったことを特別に気にはしていない。元々フィンランド人は他人と比較する社会を求めていないから、学歴や職業、大学ランキング、企業ブランドは存在せず、それらで人の価値を決めるようなことは無い。
このような国民性に支えられながら、信頼され、尊敬される教師はどのように養成されてきたのか。1990年代、失業率20%、深刻な不況に見舞われたフィンランドは、国を立て直すには人への投資が重要と考えた。全ての子供が教育を受ける権利を保障し、それを実現するために国は現場を信頼し、質の高い教師を養成することを改革の柱に据え、国家や行政は余計な口出しをせず徹底的に任せるシステムを確立することで優れた教師を育てたのである。
(2010年7月3日号)TOP PAGE 「教育の理想と現実」リスト
「競争が歪める心豊かで健全な成長」
-
日本の教育に点数主義が導入されたのは1960年代後半、筆者が中学校の教員だった頃ころである。戦後第一のベビーブームで誕生した子供たちが中学生になり、生徒数が急増した時期に当たる。当時、1学級の生徒数は48人前後、高校進学率は55~65%であった。この辺から進学競争が次第に激しくなっていくのである。
一方、子供たちの家庭環境や生活環境が激変してくる。核家族化が進み、夫婦共働き、出稼ぎなどの増加に伴って、いわゆる保護者の『不在家庭』(文部省の1969年調査で小学生全体の20%、中学生では23 %)やカギっ子の問題が深刻になる。一人でのテレビ視聴や食事などの問題も出てきた。また、親子や師弟間の冷えた関係は少年の非行化に拍車をかけることになっていく。少年犯罪の増加や家出少年の増加、そして長期欠席も増えていったのである。
ここで注目すべきはこういった非行が必ずしも生活困窮家庭の子供や学習成績の悪い子供に限ったことではなかったということである。その理由の一つに考えられることは、テスト中心主義が学校はもとより日本社会全体に広がりつつあることへの子供たちの直感的な危機感の表れであったと思われる。勤務校の一部の教科担任が期末や中間テストの全生徒の点数を職員室前の廊下に張り出すのを見て、これはもう義務教育ではない! そんな憤りを感じたのもこの頃である。期を同じくして学校に来ない生徒がぼつぼつ出始めると共に、家で睡眠薬(当時はナロン)を常習する生徒も現れてきた。また、番長などという言葉も使われ始めた頃でもある。
筆者はこれらのいずれの生徒をも担任したが、その経験を通して見えてきたものは、背景にある進学競争の激化であった。この時代は「せめて高校、できれば大学までいかせたい」という親の願いもあり、戦後30年で高校進学率は2・5倍、大学も2倍に急増するといった競争主義の始まりであり、その入り口に子供たちはいたのである。この競争が豊かな人間性を目指すべき初等・中等教育を大きく歪ゆがめることとなり、子供たちの心の豊かで健全な成長を蝕むしばみ始めたといえる。この後、日本は子供たちの経験や主体的な学びを重視する『進歩主義教育』を捨て、『画一的に教える教育』『国による管理教育』へと突き進んで行ったのである。
(2010年6月19日号)TOP PAGE 「教育の理想と現実」リスト
「日本にもあった真の教育」
-
日本に真の教育が全くなかったわけではない。戦後、1960年頃までの学校には教育の自由とゆとりがあり、教職員は子供や保護者は勿論(もちろん)、地域住民からも信頼されていた。それだけ責任も重いが、遣(や)り甲斐(がい)もあると教職員の誰もが感じていたことは確かだ。
1955年4月、筆者は新米教員として子供達の前に立った。その時、子供達の澄んだ瞳に自分の心が吸い込まれて行くような錯覚を覚えた。その出会いは衝撃的であり、以来、夜も休日も一時たりとも子供達のことが脳裏を離れることは無かった。子供の凄(す)ごさ、偉大さはこうして筆者の心を虜(とりこ)にしたのである。
当時はまだ宿直があり、夜には子供達や地域の人々が遊びに来た。休日は子供達を連れて公園や遊園地に出かけることも自由にできた。自由といえば、時間割も子供達の状況に合わせて変えることもしばしばで、例えば、雪が降れば雪合戦、興味が集中する実験や観察には思う存分時間をとる。午前中を図工と運動の時間にしたり、午後は転校する子のお別れ会やその練習に使ったりする。教育内容や方法について校長も教委もとやかく言われることは全(まった)く無かった。授業時数の報告もない。授業の形式は一斉授業ではあったが、その中で個別指導は十分に行われていたし、子供達同士での教え合いも自然な形で根付いていた。全ての学習が体験から学ぶ総合型の学習であり、遊びもふんだんに取り入れられていた。
更(さら)に、放課後は毎日のように「お残り勉強」なるものをしていた。理解が遅いとか、病気や欠席などで進度の遅れている子供達の個別指導である。これが子供達には好評で、残らなくてもいい子供達まで一緒にお残り勉強をするようになった。また、簡単な自作テストはしたが、他と比較するものではなかった。今のような競争も成績によるランク付けも無く、子供達はのびのびとしていて、どんな時でも助け合い、協力し合い、学級は和気あいあいとした家庭的な雰囲気を漂わせていたものである。勿論、不登校も、いじめもない。
この頃の日本は『教育の自由』と『子供中心主義の教育』の理念が基盤となり、デューイの教育論『経験主義』、ヨーロッパ諸国の『平等と個性尊重の教育』も存在していた。従って、教育の市場原理や競争・点数主義などは当時は想像すらできなかったのである。
(2010年6月5日号)TOP PAGE 「教育の理想と現実」リスト
「古い教育観で病む日本社会」
-
20世紀前半の米国の哲学者・教育思想家デューイの「経験の再構成理論」を概括すれば、教育は子供の日常生活経験を基礎にして個人を知的、道徳的に発展させ、反省と判断力による内的抑制によりさらに高次な社会目的にまで発展させることができるというもので、経験の教育的価値の大きさを論じている。
この経験重視の教育は、戦後間もない日本でも取り入れられたことがある。その時はデューイの理論を消化できず、「這(は)いまわる経験主義」と批判され短命に終わった。それから約半世紀、再び日本で蘇(よみがえ)ったデューイの教育論が、一人一人違う子供の体験を教材化する「総合的な学習」。子供自身の日常経験が持つ高次な教育価値を教材として活(い)かせば、学習の原動力となる好奇心や探究心を喚起し、独創力や意欲を高め、成長を飛躍的に向上させられる。
デューイの著書『経験と教育』の訳者・市村尚久氏はあとがきに「デューイは今日及び将来の学校教育の真のあり方に計り知れない展望と教育目的と方法についての示唆を与えている」「総合学習の唯一の哲学的理論書である」と書いている。日本で今日尚(なお)、大人の経験や過去の知識・技術を教材とする伝達的教育を妄信していると思われる多くの親や教員、行政職員などには是非一読を薦めたい書である。
さて、今年に入って本欄でヨーロッパ諸国の教育、そしてデューイの教育論と続けざまに紹介してきたのは、世界の教育の現実と教育の本質論から見た日本教育の実態を見極め、これからの日本教育の在り方を真剣に考えなくてはならないと思うからである。デューイの教育論を実現しているヨーロッパ諸国に対して伝統的教育から未(いま)だ抜け出せない日本。この違いが日本の子供達及び日本社会が病む状況を作り出していると考えられる。学力格差、不登校、いじめ、大人のひきこもり、コミュニケーション力の低下、人間性の劣化などは日本人が未だに持ち続けている古い教育観のためといってよい。
デューイは「教師の側から知識を授けるよりも、まず知識を求める動機を子供が持つような学校が真の学校である」、トルストイは「教育の唯一の方法は経験であり、唯一の基準は自由である」と言う。「総合的学習」「個別学習」「体験学習」「教育の自由」等の価値が分からない社会に、真の教育は無い。
(2010年5月15日号)TOP PAGE 「教育の理想と現実」リスト
「『知性の自由』がない伝統教育」
-
20世紀前半の米国の哲学者・教育思想家デューイは、教育で最も重要なことが受験目的のような教科内容を単に習得することなら将来もっと重大なことが起こるだろうという。何故(なぜ)なら、実際に生徒が生涯において出会うであろう様々(さまざま)な状況に適切に対処できる能力、生得の能力までが奪われることになるからで、それは「教育学的には最大の誤り」であると断言する。その上でデューイは、教育を受けなかった人について「教育を受けなかったが正規の学校教育の欠如が確かな財産になっている人によく出会うものである。そのような人たちは少なくとも、その人ならではの固有の常識と判断力を持ち、それを生活における実際の条件のなかで行使し、それによって自己の経験から学ぶという貴重な才能が与えられてきたのである」という。つまり、誤った教育なら受けない方が余程(よほど)ましというのだ。学歴信仰への警鐘であり真実でもある。
また、「自由の本性」については「永遠に自由である唯一の自由は『知性の自由』である」が、その自由が伝統的な教育には全(まった)くないのだという。「学校教育では据え付けられた机が配列されており、規定された合図によってのみ移動することが許される生徒達は軍隊的に管理されている」。このような行動の制限は生徒の知的・道徳的な自由を大きく束縛する。また、強要された静粛や黙従は、生徒たちが真の本性を明示する妨げとなる。
更(さら)に伝統教育にはもう一つ、教科と方法の機械的な画一性という問題があり、教育手順は多分に専制的であるという。その伝統教育が生徒や教師に与える影響については、生徒は「人為的な画一性を見せることが強いられるから有りの儘(まま)の存在としてではなくその前に気配り、礼儀正しさ、服装という外見的見せかけで繕うことになる」。しかし、目に見えない背後で生徒は、規則に反するような方向あるいは禁止されているやり方で行動しているものだという。そして、伝統的学校に見られる非社会的性格はその種の学校が静かにすることを基本的な徳の一つに挙げている事実があるとも。
『知性の自由』についてはこう述べている。「自由が全く欠如してしまっては個人が自分の知性それ自体を働かせるに必要とされる新しい教材との接触が断たれてしまうことになる」と。日本の教育は大丈夫か。
(2010年5月1日号)TOP PAGE 「教育の理想と現実」リスト
「日本の伝統的教育は個性を阻止」
-
日本に今なお根付く伝統的教育をジョン・デューイは著書『経験と教育』(1938=昭和13=年)で、すでに次のように批判している。「伝統的教育とは過去の知、技の伝達が任務であり道徳的訓練は規準や規律に適合するように、行為についての習慣形成をすることによって成り立つというものである。従って生徒の学習態度は概しておとなしく受身で従順でなければならない。他方、教師は過去から伝わる教材に効率よく結びつけるための代理人に過ぎず、伝達と行為の規則強要のための仲介者なのだ」、そして、その為(ため)の学校は「机、黒板と校庭があれば十分だ」と。
デューイによれば「伝統教育の本質は、大人の行為規準(道徳)と教材と方法とを押し付けていくことであって、子供が教えられるものは社会の文化的所産であり書物や大人の頭の中に組み込まれているもの」で、それを子供は習得する。従って「子供達の経験の範囲を超え子供が現に持っている能力とは無縁なもの」となる。このような「上から教え込む教育は個性の表現と育成を阻止することになり、外部からの訓練は自由な活動を阻止することとなり、知的道徳的発達を制限することになる」という。伝統的な教育は、学ぶ者と教えられる者との隔たりが如何(いか)に広く大き過ぎるかが分かる。
更(さら)に伝統的教育の誤りについて「将来のある時期に役に立つだろうということだけで教え学ばせる算数、地理・歴史など一定量の教科内容を単に習得するだけで、そのような経験の準備的な効果があると仮定するならばそれは誤りというもの、また読み方や数え方に熟達する技法を習得すれば、それが習得された条件とは非常に異なった条件のもとでも、それらの技法を正しく効果的に利用するための準備が自動的に出来上がると仮定するのも誤りである」「殆(ほとん)ど誰もが、自分の学校時代を顧みて在学中に蓄積したはずの知識が現在はどうなってしまったかと疑っている」と言い、教科学習が単に受験目的になされることだとして片づけてよいわけはないとも言っていることに注目したい。そして教育学的には「人はその時点で学ぶ特殊な事柄だけを学習する考え方より、好きなことを持続させ嫌いな事を耐え忍んでいく態度」の形成の方がはるかに重要であって、継続無き学習は将来に禍根を残すことになろうと警告する。
(2010年4月17日号)TOP PAGE 「教育の理想と現実」リスト
「経験重視するデューイの教育論」
-
1900年代以降、今日まで欧米の教育改革・教育革新に大きな影響を与えたのが、20世紀前半の米国を代表する哲学者・教育思想家ジョン・デューイ(1859~1952)の『真実の教育は全て経験を通して生じる』という経験主義教育理論である。子供一人ひとりの経験が好奇心を喚起し、独創力を高め、学習を継続していこうとする願いや態度をつくりだす。その経験が将来の経験との相互作用によって更(さら)に高次な生きる力になるというものである。21世紀の欧米教育においてもこの教育論が教育の根本原理となっている。
ところが、日本は1880年代にドイツから軍国主義を取り入れ、形だけの実質を伴わない代議員制を持つ憲法と、所謂(いわゆる)、従順さを強要するための普通教育制度と、国家への奉仕を態度化する為(ため)の中等及び高等教育制度を設け、その制度は今でも伝統教育として根付いている。その為に国家は高度に中央集権化され、権力を持つ者が重んじられるようになり、軍隊を発展させ、後には官僚の権力を強大にさせることになる。
当時から現代にかけて世界の教育に多大な影響力を持っていたデューイは1919年に来日したことがある。その時のデューイは現在の日本女子大学や東京大学など各地で講演し好評を博したと伝えられていて、なかでも日本女子大学の学長に宛てたメッセージがよく知られている。それは当時の日本人に対するメッセージでもある。「どんなことでも少人数の人ではなく多くの人が助け合ってこそ成功する。共通の利害の観念を持つこと、人の利益を己の利益とし、人の損を自分の損だとする。そしてお互いを信用すること。そうすれば必ず繁栄の日がやってきます」というもの。他にも「日本人は、例え考え方が反対のもの(民主主義と専制主義のような)でもすぐ飛びつく。ドイツを真似(まね)た体質を残したままの日本。官僚中心主義が民主主義を壊しているから日本の民主主義は脆弱(ぜいじゃく)なのです」「日本は西洋と東洋に対する外交が余りにも違う」などの言葉が残されている。今から90年も前にデューイが指摘した日本社会及び日本の教育が今なお古くなってはいないことに驚く。
次回からは、デューイの著書『経験と教育』(講談社)をもとに、日本に今なお根付く伝統教育の問題点を3回にわたって検証する。
(2010年4月3日号)TOP PAGE 「教育の理想と現実」リスト
「日本的な教育で失敗
~見過ごせないイギリスの改革」
-
教育先進諸国EUといってもイギリスの教育は改革によって失敗した。それも日本の教育がモデルというから、我が国は対岸の火事として見過ごすことはできない。
改革以前のイギリスは他のEU諸国と同様、教育は基本的には自由であり、多様性が認められていた。学習は子供の様々な経験を通して学ぶものという考え方が貫かれ、個々人の能力と進度に合わせて課題を解決していく個別学習など、一人ひとりの状況に応じた実質的に平等な教育を実現していた。具体的には、特別指導の必要な子供の教育を普通学級で行う統合教育や落ちこぼれをなくす教育など、弱者の立場に立つ教育方法が取り入れられた。クラス人数は25人以下で、同時間内に個人のペースと別々の内容で学習ができ、特別なニーズのある子供には補助教員がつく。異年齢交流の場を多く取り入れて子供同士の絆きずなを強めるなど、取り組みも多様であった。
『教育は知識を注入することではない』というのがEUの教育観であるが、イギリスでも1967年ブラウンデン報告を機に知識の詰め込みとしての教育は否定された。ところが1988年、サッチャー政権による市場原理主義の教育改革によって大転換されたのである。成立した新教育法は教育の原理から制度や授業方法までを変えるもので、イギリスの教育観を一変させた。サッチャー政権が目指した中央集権化した管理社会構築の理念を受けて、教育分野でも国家カリキュラム(日本の学習指導要領)や全国学力テストを導入して教育内容や学力の国家管理の体制を確立した。これによって、学校では国の定めた知識や技能を画一的に教え、国家で規定した統一的な内容を教科書に基づいて一斉授業で教師が教え子供が学ぶという日本的な教育体制を復活させたのである。
その結果、皮肉にも国際数学・理科教育動向調査(TIMSS)では学力が低下、政府は躍起になって学力向上を目指すものの、その後も目標未達状態が続いた。それだけではなく、子供・親、それに教師までもがテストの点数競争に巻き込まれることになり、教育の本質である人間教育はおろそかになっていった。その為ため、いじめ、薬物乱用、不登校、停・退学などの増加や教員がテストに備えて教えること、模擬テストをすること、校長までがテスト時に正解誘導をすることといったように教育全体に歪(ゆがみ)が起こった。学力テストの成績による学校選別で地価高騰を招くといった笑えない話もあるという。ただ現在では、教師や校長の努力によって国も本来の教育へと舵かじを切った。日本はこれを他山の石とできるかどうか。
(2010年3月20日号)TOP PAGE 「教育の理想と現実」リスト
「『画一的』維持では変われない
~改革・革新繰り返すドイツ」
-
日本では画一的な教育が真の教育だと思い込んではいないだろうか。もしそうであるならば、日本の教育はこれからも変われない。
1880年代、日本はドイツから軍国主義を取り入れ、従順さを強要する普通教育制度と国家への奉仕を態度化するための中等及(およ)び高等教育制度を設けた。教育方法は教授(学習指導)と訓練からなり、全国一律の教育内容を一斉指導で行う画一的なものであった。
訓練を象徴する教科が体育であり行事の運動会である。運動会は競技を楽しむ欧米と比べてみると違いがよくわかる。日本は集合、体操、行進、応援、競技のための入退場などいずれも整然と行うことに主眼が置かれ、訓練の結果を披露する場になる。他にも日本では未(いま)だにドリル(反復練習)が重んじられているが、これは理解の為(ため)ではなく理解を定着させるもので、訓練という教育方法概念である。
全国画一教育とか一斉授業、訓練など世界から見れば最もはや早教育の名に値しないものが日本では大手を振って存在している。つまり、ドイツ式の教育が1世紀以上も息づいているのである。
ところが、当のドイツは1960年代を境に複線型の学校制度、就学年齢の弾力化、総合性学校の設立など教育制度の構造改革が進められてきている。教育課程の全国的な基準はなく各州が独自に編成でき、編成基準が教科中心から教科横断的授業や教科統合授業への改編がなされ、学校の自律性を高めるための行政や学校経営の在り方が論議されている。
ドイツの子供の一日を初等学校から見てみよう。登校時刻は学校によって異なり、学校全体の始業時刻はなく、1時限目の授業があるクラスとないクラスでは登校時刻は違い、全校集会や朝礼などはない。教科はドイツ語、算数、事実教授(統合教育)、美術、音楽、体育、宗教(倫理)で3年生からは外国語が加わる。ドイツ語、算数、事実の3教科は時間割に入れてあり、何をやるかは教員の裁量に任されている。2・3時限目の間の休み時間は天候が悪い時を除き校庭に出て遊ぶ決まりになっている。チャイムで入室後は果物やパンの間食タイム(2回目の朝ご飯と呼ぶ)。伝統的にドイツの学校は午前中で授業が終わる半日制で部活はない。給食もなく家庭で昼食、午後は地域の乗馬やサッカークラブ、絵画や音楽教室に通う子供が多い。
近年、社会の変化に対応した質の高い教育を提供できる学校の在り方が模索されている。日本教育の原点となったドイツは時代や国際社会の変化に伴い改革・革新を繰り返している。しかし日本は何も変わっていない。
(2010年3月6日号)TOP PAGE 「教育の理想と現実」リスト
「『自分で考える教育』行き渡る
~平等と個性両立のフィンランド」
学校の一日。冬まだ暗い午前8時から同9時にかけて子供達が登校、自分の授業のある時間までに登校するので全校一斉とはならない。授業時間は学校独自に決める。1時間ごとに休みを取ることも2時間続きにするのも自由、休み時間は6年生までは必ず外で遊ぶ決まりになっている。その間教員はティータイム、コミュニケーションの場へ。昼食はカフェテリアでする。授業が終わると学童保育(始業前も行ける)に行く子供以外は帰宅、教員も退勤する。
子供達には小さい時から自分の人生は自分のもの、どうするかは自分で考えなくてはいけないという教育が行き渡っている。その為(ため)、何事も他人のせいにはしないし、大人からも勉強を強制されることはない。学校制度は1999年、基礎学校法改正により9年一貫制、異年齢の複式学級制。学習未到達生徒のための10年生プログラムである補習授業が用意されているから自分のペースで学べる。2学期制が一般的、年間授業数は190日、7歳から14歳までの総授業時間数はOECD加盟国中で最短。上級中学校または職業学校への入学試験はない。更(さら)に高等教育(大学)に進学する場合は大学入学資格試験を受ければよい。いずれの学校も格差はない。
次に、中央(国)と地方(自治体)の学校の権限分担であるが、中央はガイドライン役に留め教員など専門スタッフの支援に徹し、中央行政の権限を条件整備と情報提供に限定している。国家カリキュラムは大綱とし、教育課程は地方自治体が決め、学習内容、時間割や教科の組み合わせなどは教員が決める。これまでの一斉授業は批判され、子供個々のニーズや能力に合わせた教育(個別化授業)が行われている。勿論(もちろん)、全国一律の教育内容などはないから、比べるための一律の学力テストもない。検定教科書もなく、必要ならば資料として教師が採用する。大学まで無償のフィンランド教育である。
(2010年2月20日号)TOP PAGE 「教育の理想と現実」リスト
「『画一』から『個別』へ
~オランダに学ぶ教育改革」
初めに、オランダの小学校の授業風景から。子供は数人のグループを作って勉強しているが、何時(いつ)も席にいるとは限らない。コンピューター・読書・資料棚・ゲームなどの様々なコーナーで、それぞれが違う課題をこなす。先生は子供たちの間を静かに回りながら必要に応じてアドバイスをしたり質問に答えたりしている。よくわかっていない子供には、教室の隅に供えられた多くの教材の中から子供の学習状況に合ったものを取り出して与え、教えるのではなく子供が自力で理解するよう助力する。課題を終えた子供は、廊下やホールの明るい窓のそばなどでその時間の教科以外の追加学習に取り組んだり、パズルやゲーム感覚でできる挑戦的な課題に取り組んだりしている。
オランダでは子供を椅子(いす)に縛り付けておくことはない。では、何故(なぜ)このような自由な雰囲気の中で、どの子供も一生懸命課題に立ち向かっているのか。それは、戦後の急速な産業発展がもたらした物質偏重の価値観に対するオランダ国民の疑問と、凄まじいばかりの市民の意識変革による。伝統的なオランダ社会の構造をも大きく揺さぶる中で、大掛かりな教育制度改革「画一から個別へ」が国民合意のもとに進められた結果である。
改革は1969年にK・ドールンボスが書いた『落ちこぼれへの抵抗』に始まる。彼は、落ちこぼれの問題はまさに「旧来の画一的な一斉授業が生んでいる」と指摘し、落ちこぼれのない教育「オールタナティブ教育」に学ぶべき―とした。改革の骨子は、画一授業と教科制や科目ごとの時間割の廃止、柔軟なカリキュラムを認める(総合学習)―などで、学校がより自由な教育活動を展開できるよう保証した。特に、社会的環境に恵まれない子供への配慮と、一人ひとりの能力やテンポに合わせて学びを支え励ます―などが重視された。結果、〈非競争社会〉の理念とオランダ人の誇りとしている〈教育の自由〉の原則が土台となり、子供の自立心や共同性を重視した個別教育が主流となっている。
制度的には大学まで無償。個別化に対応するための少人数学級で、授業時間は世界で最低レベル。大学(医学部を除く)まで入試はない。当然のこと学習塾もない。教科書検定もない。これがオランダの教育である。
(2010年2月6日号)TOP PAGE 「教育の理想と現実」リスト
「教員の工夫や自主性を制限
~世界に遅れる日本の教育」
まずは学校教育の現状。残念ながら世界から見ればかなりの遅れをとっていると言わざるを得ない。1990年代後半にそのことに気付き、民間出身の文部大臣(当時)の教育改革によって21世紀への展望を見出したのが1999年の『これからの教育』(中教審答申)。しかし前政権はこれを否定し、その結果、日本の教育はこの数年、急速に過去への逆行が起きている。その原因が国際学力調査PISA(OECD生徒の学習到達度調査)やTIMSS(国際教育到達度評価学会の国際数学・理科教育動向調査)に端を発する学力低下論である。これに勢いづいたのが授業時数削減を伴う前指導要領導入時に反対を唱えた学力低下論者であり、危機感を煽(あお)るメディアと世論に押された文科省が前指導要領の完全実施直前にブレーキを踏まないまま突然バックギアに入れたことに全てが始まる。教育の本質である「ゆとり」を悪者にし、更(さら)に安倍政権が相乗りして世界の教育の流れに逆行する方向へアクセルをいっぱいに踏み込んだのである。現場は大混乱に陥ったが教育の中央集権化が確立されている日本では、国主導の政策に教育委員会・学校は従わざるを得ない。
20年も前に個性尊重教育と言い出しながら画一金太郎飴(あめ)学校から未(いま)だに抜け出せない日本の学校。その授業風景を覗(のぞ)いてみよう。箱型の教室、前面に黒板、机が黒板に向かって縦横揃(そろ)えて整然と並び姿勢を正した子供達が座っている。教壇は無くなったものの先生は黒板の前に立ち、子供と対面状態で授業が進む。教室内は静寂で、時折「ハーイ」という揃った声が聞こえてくる。最近では授業中に立ち歩く子供も目立つようではあるが、ほんの一部であり集団不適応児などと特別扱いする。これがいわゆる講義式の日本型一斉授業であり、世界では稀(まれ)な授業形態ともいえ、日本にはティーチングはあるがラーニングが無いといわれる所以(ゆえん)でもある。しかも国が教育内容から授業時数、教科書までを一律に決めて教員にあてがい、従わなければ罰するという民主主義国家では考えられない教育システムを確立している。教育現場はこのことによって縛られ、教育の前提である『自由』がなく、教員の創意工夫や自主性は制限される。更に、突然に不条理な教育の転換が行われても現場は意見を言うことすらできず問答無用と切り捨てられ、追従せざるを得ない。これが日本の教育の現状である。
一時期、世界の潮流に乗ったかに見えたのも束(つか)の間、日本の教育は世界から取り残されることが決定的になった。
(2010年1月16日号)TOP PAGE 「教育の理想と現実」リスト
「新政権の3つの理念は
日本教育の希望となる」
-
今年は久々に日本の教育に希望が持てそうだ。現役時、後半の任期4年間は教育の本質に理解と認識の無い首長との間に軋轢(あつれき)や葛藤(かっとう)があったが、子供や教育の本質を見つめ信念に基づいて子供たちの未来の幸せを実現すべく、教育に理解ある同志と先輩の支えを得て全力を傾注できたから常に夢や希望があった。それが退任後は国の教育政策の急速な劣化を見ているうちに全く夢も希望も持てなくなったというのが正直なところである。
しかし、政権が変わってこの数か月、筆者には教育も変わるぞという確かな手応えが感じられる。現政権の教育変革の柱は大きくは2つ、地方主権(地域の自立)と地域・家庭・学校相互の信頼の回復にある。いずれも教育の根幹をなすものであって筆者が教育委員会で推進してきた教育の理念・方針や、退任後、参議院での公述及び本欄で訴え続けてきた教育観と一致するもので、現実に絶望しながらも久しく待ち望んでいたものである。また、これらは日本の教育が長いこと抱えてきた大きな課題でもある。前政権までの一時期、数の力で教育基本法や教育三法を変えるという強行策に出た時は日本教育の将来に強い危機感を覚えた。当時の政府が意図したのは子供のためではなく国家のための教育改革であることが明らかだった。当時、良識ある国民は勿論(もちろん)のこと与党議員でさえ首をかしげる人たちが多かったことが記憶に新しい。昔から、大きく振れ過ぎた振り子は何時(いつか)は反対方向に戻るといわれてきたがそれを待っていられないのが子供の教育である。子供の成長は待ったなしでありその発達段階に応じた適時的確な教育環境が必要である。いつの時代も子供はその時代や社会の環境を真正面から受けとめながら間断なく成長の歩みを進めているのだから手抜きや先送りはできない。
このようなことから新政権に筆者が特に注目しているのは、第1に子供たちを社会全体で育てるという理念である。関連する政策には子育て支援や高校授業料の無料化、奨学金制度の拡充などがある。教育は国民に等しく与えられるものであるという憲法の精神からすれば子供を持つ家庭の経済状態による格差があってはならない。第2に、総理が引用したアインシュタイン博士の言葉『人は他人のために存在する』は、そのまま『人間性』と『友愛』とに置き換えることができる。つまり、教育は豊かな人間性の涵養(かんよう)を目指すということである。第3が失われた地域の絆きずなを取り戻し、人と人とが支え合い信頼しあえる社会「教育環境」をつくる。この3つの理念は日本の教育には力強いメッセージであり希望となり得る。
(2010年1月3日号)TOP PAGE 「教育の理想と現実」リスト