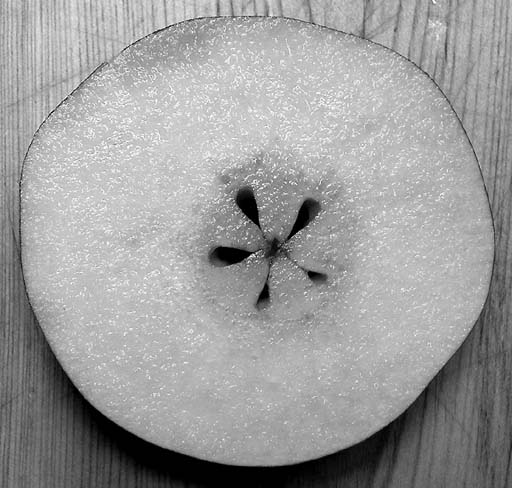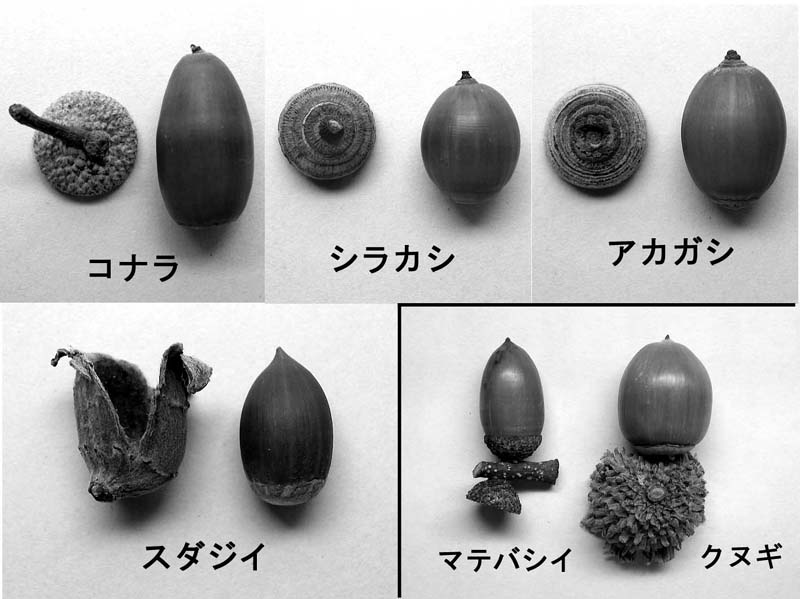東浜人工海浜の植物市川市自然環境研究グループでは毎月第三日曜日に、市内の様々な場所で自然観察会を行っている。亡くなられた石井信義先生を中心に、約三十年間続いてきた。原則として偶数月は大町自然観察園で、奇数月はその他の地域で行っている。その三十年の歴史の中で、六月の観察会は初めて海で行った。
市川が面する東京湾は昭和三十年代の終りから次々に埋め立てられ、工業用地として日本の経済成長を支えてきた。その結果、我々は生活の物質的向上を得たが、代償として豊かな自然の海に接するチャンスを失った。
経済の発展と首都の膨張が一段落した今、新たな土地需要がなくなり、市川二期、京葉港二期埋め立て計画が白紙に戻された。その副産物の一つとして市川・船橋の地さきには不要となった古い航路が、昭和五十年代終りに埋め戻された状態で残された。
この部分は埋め立て地ながらやや自然に近い形の海岸となり、干潮時には広大な干潟ができるため、テレビなどではよく「三番瀬の干潟」として紹介される。船橋側は船橋海浜公園の潮干狩場になっており、多くの人が訪れるが、市川側はほとんど利用者がいないため徐々に海岸特有の植生が復活してきている。
海岸は常に潮風や砂が吹きつけ、時には波を被るなど、植物にとっては決して住みやすい場所ではなく、塩に対する耐性の発達した植物だけが生育できる。砂浜に生育する海浜植物、塩分を含んだ水に浸っても耐性のある塩沼地植物がそうである。
東浜の場合は、自然の海岸に比べると面積が狭く傾斜も急で塩沼地もない。このため、海浜植物帯の幅も狭く、ハママツナなどの典型的な塩沼地植生もない。それでもハマヒルガオやコウボウシバ、テンキグサ、オカヒジキ、ツルナ、ホソバノハマアカザ、ハチジョウナなどの独特の植物が見られる。
しかも面白いことにウスベニツメクサの代わりにウシオハナツメクサ、ウラギクの代わりにオオホウキギクなど一部の種が同じような環境に生育する帰化種に置き換わっている。東浜海岸は三番瀬の再生を考える上で大変興味深い場所である。
次回の観察会は七月二十日、江戸川放水路で干潟の生物の観察(午後一時半、東西線妙典駅改札集合。雨天中止)。
(2003年6月27日)