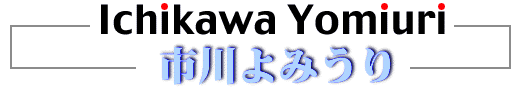
![]()
コーラスの魅力・難しさは心のハーモニー
PTAコーラス10年ぶりのコンサート委員長
安斎 美篠さん
 |
音楽の盛んな小学校でコーラスを教わってから合唱が好きになり、進学後、そして社会人になってからも、部活や合唱団でコーラスを続けた。次男が市川市立三中に通っていた20年ほど前、友人と一緒にPTAで呼びかけてフリーアンティーズを結成。学校で週1回の練習を重ねながら、学園祭や市の音楽祭でその成果を発表している。 「コーラスは音だけでなく、心のハーモニーが必要。心を合わせないと一つのものを作れない」。それが、コーラスの魅力であり、難しさでもある。毎年、仲間と開いている新年会や忘年会、暑気払いなども楽しみの一つ。10年前の初コンサートで沖縄の歌「花」を来場者と一緒に大合唱したとき、「会場が一つに解け合って良かった」ことも、忘れられない思い出になっている。 「練習会場として学校が借りられるのはありがたい」「先生は度量が大きく、メンバーを包み込んでくれる」と恵まれた音楽環境に感謝する。「続けられるうちは、歌い続けたい」。そう願う73歳は、いま、13日に迫った10年ぶりのコンサートに全力投球。「みんなで張り切って若々しくやります。来てくれた人が喜んでくれるような楽しい音楽会にしたい」。 (2007年10月5日) MENUへ |
![]()
自分の将来を見ているようでお節介に…
会話と食事楽しむなづな会代表
八町 恵美子さん
 |
「この地をついの住み家に」と決めてから、近所で一人寂しそうにしている高齢者をよく見かけるようになった。「私の将来を見ているよう」。若いころに夫の転勤で転居を繰り返し、寂しい思いをした経験から、他人事とは思えなかった。 平成3年10月、「地域の福祉を考えてみませんか」と一人でポスターを描き、自分の住んでいるマンションの掲示板に張って仲間を募集。当初18人だった会員は、いまでは約85人に増えた。支える人、支えられる人を区別せず、「お互いに支えあう」というのが基本的な考え。月に一度、自分たちで調理する手作りの会食会には、60人前後の会員たちが楽しみに集まる。 趣味のカメラを始めたのは、20年以上続けている山歩きがきっかけ。「山に登ったときの感動を伝えたい」と写真学校にも通い、山に解け込んだ仲間の写真を撮ってきた。いまでは、かつての田園から変わってゆく近所の風景や、会員たちの生き生きとした表情をとらえ続ける。 なづな会以外にも、子育てサークルのボランティアなど何にでも首を突っ込んでしまう自分を「お節介なだけ」と笑う68歳。だが、その“お節介”に救われている人は、決して少なくはない。 (2007年10月12日) MENUへ |
![]()
写真は個人でできるが作品発表は難しい
30回目の写真展を開いた写真グループ写友会会長
津田 芳郎さん
 |
21年目を迎えた写友会は現在、会員数27人。写真展のスペースを考えるとこれ以上人数を増やすことは難しく、「交通の便が良く、展示スペースの広い会場が市川にできてほしい」と望む。「写真は個人でもできるが、個人で写真展を開くのは難しいので、作品を発表するためだけにグループを作るのもいい」。昨年以降、同じ思いを抱く人たちと「デジタルフォトクラブ」「フォトほたる」という少人数グループを共同で立ち上げ、それぞれで写真展を開いている。 写真を本格的に始めたのは60歳を過ぎてから。「一人で長続きできる趣味を…」と、当時最新のオートフォーカスカメラを購入した。だが、それまで30年間、家族のスナップ写真などを撮っていたのはマニュアルカメラ。使い方を学ぶため、講座に通って勉強した。 その後、仕事の関係で「写す対象がたくさんあった」東北地方に3年間滞在。3年前からデジタルカメラに切り替え、風景や行事、人物など幅広い写真を、1年間で1万5千枚ほど撮り続けている。 傘寿(さんじゅ)を迎えたいま、一番の狙いは「満月が海から昇って行く風景」。レンズの奥から、そのチャンスをうかがっている。 (2007年10月19日) MENUへ |
![]()
子供の笑顔を何よりの励みにいつまでも
ボランティア功労者おむすびの会代表
赤田 秀子さん
 |
宮沢賢治の学会や研究会4団体に所属し、共著も出している宮沢賢治研究家。5年前に55歳で運転免許を取得、ドライブに出かけて賢治作品に登場する鳥や植物の写真を撮り、ブログに公開して作品のイメージを紹介している。 宮沢賢治にのめり込んだきっかけは児童文学。長男が幼稚園に通い、絵本への関心が高まっていた昭和54年、市川市信篤公民館で子供たちに絵本の読み聞かせなどを行うボランティアを始めた。日本で作られた児童文学を探しているうちに、「学校教育で教わったイメージとは違う宮沢賢治」を発見。ユーモアと表現のすばらしさにすっかり魅了された。 ボランティア活動は、「子供の笑顔が何よりの励み」と現在も保育園などで実施。「おむすびの会」という名前には、「心と体のエネルギー源」というおむすびのイメージと、「人の心と心を結びたい」という思いが込められている。 当初は子供たちのために勉強した児童文学だが、「話をしているだけで幸せな気分になる」というほど、いまでは自分も大好き。「派手なことはせず、子供たちが聞いてくれる限り続けたい」。厚労大臣から表彰を受けても、その姿勢が変ることはない。 (2007年10月26日) MENUへ |
千葉県市川市市川2−4−9 〒272-8585
TEL:047-321-1717 (代表) FAX:047-321-1718
Eメール:center@ichiyomi.co.jp