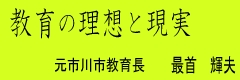
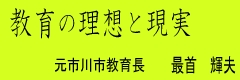
しかし、学校の役割という前提で今の学校の置かれている状況を見る時、多くの理不尽なことが目に付く。
いじめや不登校に始まり、子供時代の非行から成人した後の引きこもりや人間性・人格の問題まで、教育が悪いから、学校がだめだからという。本当にそうなのだろうか。
本来、学校教育は万能ではなく、できることは限られる。学校がきちんと教えれば何とかなるというのは学校依存社会が生み出した幻想に過ぎない。学校にはとてもそんな力はないし、あれもこれもと押し付けられれば、いずれは本来の役割もろともパンクする。
1990年代に学校をコンビニエンス・スクールと名付けた人がいたが、名言である。当時は交通安全、麻薬、エイズ・性教育と次々と社会問題化したものは何でも学校教育へと持ち込んでくる時代だった。その後も増えることはあっても減ることはなかった。
最近では、英語指導を小学校からやると言い出し、教員養成や教員増をしないまま担任任せの見切り発車。脳の発達の面からは母国語と外国語の混乱を招くというが、その議論もないままに。また、今度は道徳教育の教科化だと言い出す始末。道徳は心の問題であって、教えるものではなく育てるもの。しかも、本来学校は一つの真、一つの善、一つの美といった単一の価値観を教える所ではない。世の中にはいろいろなものの考え方がある、と知らせる所。それを自ら体験し、自分なりに選択ができるように時間をかけてゆっくりとたくさんの可能性を見出していくべきなのであるが、今の教育はこれが正しく、これ以外はだめと決めつける。
人間は間違ったり失敗したりしながら成長する。間違いや失敗の体験を反省し、次に生かせるようになれば、自分を認められるようになる。それが成長である。問題の応急処置ではなく、人としての成長を支えるのが本当の教育であり、学校の役割ではないのか。
(2015年3月21日号)ホームページ 「教育の理想と現実」リスト